ルネサンス本がアマゾンからどんぶらこっこと流れてきたよw

「海の都の物語・ヴェネツィア共和国の一千年」1~6 (塩野七海)
「フィレンツィエ」(若桑みどり)
「ルネサンスの歴史」上下 (モンタネッリ・ジェルヴァーソ)
「ルネサンスの文化」上下 (ヴルクハルト)
「中世の秋」 上下 (ホイジンガ)
以上どんぶこっこと流れてきた本たちでごぜえやす。(何かの影響を受けているw)
この中で、一冊浮いている本がありますが、なんで中世って言ってるのにルネサンスなんだ?と思いませんか?
これは、この著者の歴史のとらえ方の違いがもたらした詩的なお題です。
この人の場合は、ルネサンスを近代の幕開けとして捉えるのではなく、中世の営みの実りの季節と捉えています。
また、ルネサンスというと、イタリアが多く取沙汰されるのに対し、その後の、フランス・ネーデルランドにおけるルネサンス史は少ないかな~と思うのですが、中世の秋は、主にフランス・とネーデルランドにおける「中世の実りの季節」を扱っているようです。
というわけで、読もうじゃないか。
「海の都の物語・ヴェネツィア共和国の一千年」1~6 (塩野七海)
「フィレンツィエ」(若桑みどり)
「ルネサンスの歴史」上下 (モンタネッリ・ジェルヴァーソ)
「ルネサンスの文化」上下 (ヴルクハルト)
「中世の秋」 上下 (ホイジンガ)
以上どんぶこっこと流れてきた本たちでごぜえやす。(何かの影響を受けているw)
この中で、一冊浮いている本がありますが、なんで中世って言ってるのにルネサンスなんだ?と思いませんか?
これは、この著者の歴史のとらえ方の違いがもたらした詩的なお題です。
この人の場合は、ルネサンスを近代の幕開けとして捉えるのではなく、中世の営みの実りの季節と捉えています。
また、ルネサンスというと、イタリアが多く取沙汰されるのに対し、その後の、フランス・ネーデルランドにおけるルネサンス史は少ないかな~と思うのですが、中世の秋は、主にフランス・とネーデルランドにおける「中世の実りの季節」を扱っているようです。
というわけで、読もうじゃないか。



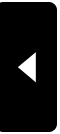

僕、ヴェネチア、好きなんだよね。天野こずえ『ARIA』の影響で。
塩野七海、トライしたいんだけれど、まだまだなかなか手が伸びないよ。『ローマ人の物語』も。読むとしたら、『ローマ人の物語』が(「海の都の物語」よりも)先かしら?
とりあえずいまは、ガルシア=マルケスなんだけれどね。
今のところ、読むなら、「ハンニバル戦記」「すべての道はローマに通ず」くらいかなあ、まあでもこれだけでも文庫で5冊になっちゃうんですよねw
ヴェネツィア本は、かなり前に買ってまだあまり読めていない新書があるんですけど、
「迷宮都市ヴェネチアを歩く」というお題で、13通りの歩き方が紹介されています。
写真も豊富で助かるのですが、私の頭に何か欠落部位があるようで、地理を文章説明されてもうまく思い浮かべられなかったりしてます。
ガルシア・マルケスですか~
また教えてください。
彼(35歳くらい??)によると、「教皇による政治時代」が、退屈らしいですね。
僕は歳をとって65歳くらいになって、「人生を達観し始めた頃」に、「読む本もとくにないから、トライしようか…」みたいな感じで読み始めようかとイメージしています。
それまではまだまだガツガツ読みたい本を読むつもりです。笑
マスターさんがどうしてつまらないと思ったか解らないですが、
歴史としては、ローマが滅んでも存在し続けて、中世ヨーロッパに重大な影響をおぼすと思いますので、つまらなくても、重要な部分ではあると思います。
教皇って存在がなぜ出現するかもまだよく解らないし。
歴史としてはかなり重大な局面なのではないかな?と思うんです。
弟夫婦がイタリアに新婚旅行へ行ったので、旅の思い出話を聞こうと思い、昨年、放送大学の『芸術史と芸術理論』のテキストと放送を録画しておいたのを久しぶりにみたんです。
テキストの中で若桑さんの本も紹介されていましたが、テレビの放送のほうでは講談社現代新書から出ている森田義之さんの『メディチ家』がいい本だって紹介していましたよ。
私は歴史が苦手で読んでも、するーっと抜けてしまうのですが、とぅらんくさんなら興味深く読めるのではないでしょうか。
貴重な情報ありがとうございます^^
歴史、好きなのですが、読書の方はスローでしか前進できないでいます。
どうしてイタリアでルネサンスが花開いたか、のあたりを最近やっと理解したばかりだったりします。
講談社現代新書の森田義之さんの「メディチ家」ですね。探してみます~