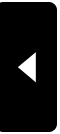ども。とぅらんく歴史研究部部長です。
歴史って苦手な人が多いですね、どうしてだろう?さてはあれだ、年表を覚えるだけのお勉強のあたり、
それじゃ相当つまんないですよね。
歴史は、現代がどのようにして形作られたかを知るための学問でもあるのです。
ですから、これから時代がどうなってゆくのかを知るキーワードにもなりますし、現代という時代にただただ飲み込まれないで、現代という風潮を少し離れた所から見る助けになるのです。
繰り返してはならない悲惨な出来事の多かった20世紀に学ぶこともできます。

そもそも、どのように、現代が存在するようになったかは、自分的には、欧州の中世の終わり、近代の始まりのあたりから調べてみるのが良いかと思います。
かなり簡単にぶっ飛ばしますw
中世末期、東ローマ帝国がオスマントルコに敗れ、ローマ帝国滅亡。
欧州全域に強い影響力を持ち続けたカソリックの力がなぜ弱まったのか?ここは肝心と思います。
とりあえず、何となく、マルコ・ポーロが東洋に行って帰って来た時に「東方見聞録」書きますね。この影響力強いでしょ?この人商人です。シルクロードを通って、当時の元、クビライ・ハーンのもとにある程度とどまったようですね。
旅商人の見聞録の力は強かった(たぶん)
中世は宗教の世界観がすべてで、それを信じない者は、どうなったことやら…
何といっても、聖書を読んではならないって言うあたりがおかしいです。
聖書を読んだりさわったりするだけで、火あぶりですからね。
魔女狩りってのもあったね、この時代、相当の女性が消えたんだと思います。
マルコ・ポーロだけじゃないにせよ、世界って、宗教が言っていることと違うんだ!と人々が気付き始める。
そして、宗教に対する信頼も薄れる。
そして、世界を自分の目で確かめたいという人が増える。
大航海時代前夜なのではないでしょうか。
自分の目で確かめる。これが近代の思想や諸学問の土台となります。
宗教も弱体化する。
カソリックに対抗する勢力が現れる。ひたすら聖書に記されている通りに生きるべきだ!という集団、すなわちプロテスタント。
そして宗教戦争の時代が始まる。
大航海時代も宗教戦争も同じ時期に発生するのはこのためと思います。
芸術の目覚めのような時代でした。
ルネッサンスですね。
ルネッサンスは科学の夜明けのような文化と思います。
世界認識がすっかり変わっていくので、精神のありようもまた激変します。
この時代から油彩が急速に進歩するというか、遠近法が出てくるですね。(たぶん。。)

冒険者の時代、マルコ・ポーロがアメリカ大陸を発見(欧州的には初めての発見)
アフリカの喜望峰を超えて航海し、インドから胡椒を買い付けて戻ってきたのは、バスコ・ダ・ガマ
いろんな冒険家が世界を行き廻るうちに、帆船もどんどん進化を遂げて行きます。
この辺りから、欧州が競争するかのように、いろんな国を滅ぼし植民地にして行きます。
かなり乱暴です。
アフリカの奴隷売買など、悪いこといっぱいするからつらい。
宗教戦争はかなりの間続きます。
難を逃れて清教徒が(プロテスタント)が、ガレオン(帆船、おそらく多少武装していたと思われる)でアメリカに渡ります。
アメリカでは、コロンブスが人民平等を唱えますが、ネイティブアメリカンの人たちや、奴隷として連れられて来た黒人さんたちはさんざん虐げられます。
この歴史があるからこそブルースやジャズという芸術が発達するのですが。
宗教戦争のもたらしたものは、宗教なんかもういいや、という諦め感でしょうか、
19世紀は理神論者や無神論者の人が続々登場です。
世界が宗教が言ってるのと違った、という認識と、宗教の醜態。ガリレオの地動説の宗教裁判、(しかし彼は聖書を信じていた、彼はカソリックの教えと聖書は違うと確信していた)
ダーゥィンの進化論、そして二ーチェの「神は死んだ」。
そして20世紀初めにフロイトが「精神分析入門」刊行。
ルネッサンス期の基本の考え方である、デカルトの「我思うゆえに我あり」(コギト・エルゴ・スム)が終わりを告げます。二元論、今でも普通に暮らしているときはこれで十分ですが。(心と体は別々に存在している)
20世紀は唯心論も理神論も終わり、唯物論の時代だったと思います。
西洋が自らのルーツを失う。思想がどどどーと荒波立てます。
人間が偶然に生じたということになったので、「存在不安」という言葉が生まれます。
今時の思想や諸学問はニーチェに端を発している感じがします。

西洋の学問のピンチに立ち向かおうと、フッサールという哲学者が、思想の土台を据え変えろ!と、現象学という視野を提唱します。(世界認識を判断停止にする(エポケー)ことによって見えてくるものからまず情報を組み立て直すというか……つまりはゆがんだ客観(間主観)を捨てて、生まれたての目で始めろと言っている感じでしょうか)
とにかく西洋のなんでも所有精神により、ほかの諸国家は虐げられ、滅ばされた。
日本は何とか滅ぼされなかったけど、不平等条約を強制的に結ばされてしまった。
力でねじ伏せます。
西洋風の教育が世界を行き廻る。
西洋風の体の動かし方が普通になる。(日本人は、明治以前、今の日本人とは違う体の動かし方をしていたようです。それが、今の、柔道とか合気道とかの武道の中に残っているのだと思うのですが、どうなんでしょう?)
第一次大戦も、二次大戦も、西洋の競争みたいなものが裏にある感じがします。
科学が発達して、世界が狭くなって、世界中を巻き込みました。
何が悪かったんだろう、って、一概には言えないですね。考えるときりがないです。
最近は「世界遺産」という考え方があって、ようやく、西洋が、滅ぼした国の文化を受け入れようとしています。文化人類学?文化人類学にあこがれておりまする。
何となく、まとまりが悪い気がしますが、今日はこの辺で。。。
かなり長くなったけど、かなり短くまとまったか、あるいは独断と偏見が入ったかは、いずれ。
(やっぱり長すぎる~)

にほんブログ村
歴史って苦手な人が多いですね、どうしてだろう?さてはあれだ、年表を覚えるだけのお勉強のあたり、
それじゃ相当つまんないですよね。
歴史は、現代がどのようにして形作られたかを知るための学問でもあるのです。
ですから、これから時代がどうなってゆくのかを知るキーワードにもなりますし、現代という時代にただただ飲み込まれないで、現代という風潮を少し離れた所から見る助けになるのです。
繰り返してはならない悲惨な出来事の多かった20世紀に学ぶこともできます。
そもそも、どのように、現代が存在するようになったかは、自分的には、欧州の中世の終わり、近代の始まりのあたりから調べてみるのが良いかと思います。
かなり簡単にぶっ飛ばしますw
中世末期、東ローマ帝国がオスマントルコに敗れ、ローマ帝国滅亡。
欧州全域に強い影響力を持ち続けたカソリックの力がなぜ弱まったのか?ここは肝心と思います。
とりあえず、何となく、マルコ・ポーロが東洋に行って帰って来た時に「東方見聞録」書きますね。この影響力強いでしょ?この人商人です。シルクロードを通って、当時の元、クビライ・ハーンのもとにある程度とどまったようですね。
旅商人の見聞録の力は強かった(たぶん)
中世は宗教の世界観がすべてで、それを信じない者は、どうなったことやら…
何といっても、聖書を読んではならないって言うあたりがおかしいです。
聖書を読んだりさわったりするだけで、火あぶりですからね。
魔女狩りってのもあったね、この時代、相当の女性が消えたんだと思います。
マルコ・ポーロだけじゃないにせよ、世界って、宗教が言っていることと違うんだ!と人々が気付き始める。
そして、宗教に対する信頼も薄れる。
そして、世界を自分の目で確かめたいという人が増える。
大航海時代前夜なのではないでしょうか。
自分の目で確かめる。これが近代の思想や諸学問の土台となります。
宗教も弱体化する。
カソリックに対抗する勢力が現れる。ひたすら聖書に記されている通りに生きるべきだ!という集団、すなわちプロテスタント。
そして宗教戦争の時代が始まる。
大航海時代も宗教戦争も同じ時期に発生するのはこのためと思います。
芸術の目覚めのような時代でした。
ルネッサンスですね。
ルネッサンスは科学の夜明けのような文化と思います。
世界認識がすっかり変わっていくので、精神のありようもまた激変します。
この時代から油彩が急速に進歩するというか、遠近法が出てくるですね。(たぶん。。)
冒険者の時代、マルコ・ポーロがアメリカ大陸を発見(欧州的には初めての発見)
アフリカの喜望峰を超えて航海し、インドから胡椒を買い付けて戻ってきたのは、バスコ・ダ・ガマ
いろんな冒険家が世界を行き廻るうちに、帆船もどんどん進化を遂げて行きます。
この辺りから、欧州が競争するかのように、いろんな国を滅ぼし植民地にして行きます。
かなり乱暴です。
アフリカの奴隷売買など、悪いこといっぱいするからつらい。
宗教戦争はかなりの間続きます。
難を逃れて清教徒が(プロテスタント)が、ガレオン(帆船、おそらく多少武装していたと思われる)でアメリカに渡ります。
アメリカでは、コロンブスが人民平等を唱えますが、ネイティブアメリカンの人たちや、奴隷として連れられて来た黒人さんたちはさんざん虐げられます。
この歴史があるからこそブルースやジャズという芸術が発達するのですが。
宗教戦争のもたらしたものは、宗教なんかもういいや、という諦め感でしょうか、
19世紀は理神論者や無神論者の人が続々登場です。
世界が宗教が言ってるのと違った、という認識と、宗教の醜態。ガリレオの地動説の宗教裁判、(しかし彼は聖書を信じていた、彼はカソリックの教えと聖書は違うと確信していた)
ダーゥィンの進化論、そして二ーチェの「神は死んだ」。
そして20世紀初めにフロイトが「精神分析入門」刊行。
ルネッサンス期の基本の考え方である、デカルトの「我思うゆえに我あり」(コギト・エルゴ・スム)が終わりを告げます。二元論、今でも普通に暮らしているときはこれで十分ですが。(心と体は別々に存在している)
20世紀は唯心論も理神論も終わり、唯物論の時代だったと思います。
西洋が自らのルーツを失う。思想がどどどーと荒波立てます。
人間が偶然に生じたということになったので、「存在不安」という言葉が生まれます。
今時の思想や諸学問はニーチェに端を発している感じがします。
西洋の学問のピンチに立ち向かおうと、フッサールという哲学者が、思想の土台を据え変えろ!と、現象学という視野を提唱します。(世界認識を判断停止にする(エポケー)ことによって見えてくるものからまず情報を組み立て直すというか……つまりはゆがんだ客観(間主観)を捨てて、生まれたての目で始めろと言っている感じでしょうか)
とにかく西洋のなんでも所有精神により、ほかの諸国家は虐げられ、滅ばされた。
日本は何とか滅ぼされなかったけど、不平等条約を強制的に結ばされてしまった。
力でねじ伏せます。
西洋風の教育が世界を行き廻る。
西洋風の体の動かし方が普通になる。(日本人は、明治以前、今の日本人とは違う体の動かし方をしていたようです。それが、今の、柔道とか合気道とかの武道の中に残っているのだと思うのですが、どうなんでしょう?)
第一次大戦も、二次大戦も、西洋の競争みたいなものが裏にある感じがします。
科学が発達して、世界が狭くなって、世界中を巻き込みました。
何が悪かったんだろう、って、一概には言えないですね。考えるときりがないです。
最近は「世界遺産」という考え方があって、ようやく、西洋が、滅ぼした国の文化を受け入れようとしています。文化人類学?文化人類学にあこがれておりまする。
何となく、まとまりが悪い気がしますが、今日はこの辺で。。。
かなり長くなったけど、かなり短くまとまったか、あるいは独断と偏見が入ったかは、いずれ。
(やっぱり長すぎる~)
にほんブログ村