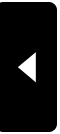こんばんわ~とぅらんく詩吟の会でございます~^^
今日は、ど素人の私が、プロの歌人の短歌を批評するというとんでもない事をやってみようと思います。^^
我が短歌人生一カ月未満の全力を振り絞って、いってみよう~^^
で、まず取り掛かるのは、短歌入口の人からですね。→小川真理子さんです。
こちらの方は、フランス語非常勤講師を仕事にしておられます。
言語の世界に深く根づいた短歌をお詠みです。
また、外国に留学されている時に、軽いカルチャーショックを受けておられる模様を短歌で表現しておられます。
この方、実はジャパニーズにしてはドライな感じの人なのかな?と思ったりします。
自分が共感した短歌を一つ。
ランボーに逢いにゆきたし贋札の両替のやうな会話を抜けて
ランボーはご存知ですか?ティーンエイジャーの時代にドカーンと謎の詩や散文を残し、20歳になったら、アフリカに消えた謎の怪人です^^
言葉に寄り添う仕事をする人たちは、その言語のバックトーンである文化や、またその文化を発祥せしめたその土地の気候や地形に敏感です。
そのことが読み取れる短歌を2つ
雨の名の乏しきフランスの雨よ、降るならばわが巡りに降れよ
甘辛き味を知らざる口をもてouiかnonかと問ひ詰めてくる
言語に寄り添う歌二つ
「真理」といふ意味消えてゆく、横文字で指名登録欄を埋むれば
真理といふ名前の理由問ふたびに丸顔ゆゑとはぐらかさるる
どうやら、名前で哲学なさったようですね。
この方、どうやら自分を達観しておられるようです。
日本にいるときにはフランスの目線が背後に、フランスにいるときには日本の視線が背後に潜んでいる感じでしょうか。
あほらしき渾名つけられはしやぎをりあつけらかんと好きと言ふため
すごいなー戦略を練っておられましたか~という感じですね^^;
この歌、ドライ⇔ウエット ドライ⇔ウエット という構造になっている気がします。
あほらしき→ドライ はしゃぐ→ウエット あっけらかん→ドライ 好き→ウエット
湿度の違いだけで考えれば、フランスと日本を2周巡った感じでしょうか。
後、言語というものは、古来から代々受け継いできたものなので、歴史を感じさせられる表現が多々あります。
たとえば、祭り事という言葉は政治のことですが、平安時代位までは本当に、祭りを執り行うことが政治だったりしたのです。神様の機嫌を取る→豊作とか。
こんな歌があります。
共にゐる時間は眠りに充てられて土のなかなるわれらならむか
この歌が詠まれた時は、すでに結婚されておられるようですが、夫君がジャーナリストの方らしく、特に中東に赴かれることが多いようで、なかなか夫婦の時間が取れない感じです。
この、土のなかなるわれらならむか が好きです。なんかすごく太古な雰囲気をたたえておいでです。土の中というのは、ママンのおなかの中です。土は女神として祭られていることが多いと思います。
ユングはグレートマザーと表現しています。
言語と密接な関係にある人は、その言語の文化背景などにも興味をもたれるのだと思います。
文語体が多いのが好きです^^
次はフランス語教師の発音に対する敏感さが見えてくる歌を一つ。
舌の上で紙風船が弾むんだ「ぽるとがる」つて行つてごらん
騙し絵の窓辺より風 洋古書の蝋紙(パピエ パラフィネ)はつかに震ふ
火をくぐりぬけたる者の寂かさよ磁気人形(プぺ・ドゥ・ポルスレンヌ)は瞬きもせず
この歌集の題名が母音梯形なだけに、ここら辺の歌は、重要と思われます。母音梯形いというのは、発音するときに口の中がどんな感じになればいいのかを図に示したものだそうです。
むむ、何だか、未知の発音に触れてみたくなってまいりました。
ではではこの辺で今日は終いにしとうございます^^
(小川さん、勝手な理解でごめんなさい~^^)
今日は、ど素人の私が、プロの歌人の短歌を批評するというとんでもない事をやってみようと思います。^^
我が短歌人生一カ月未満の全力を振り絞って、いってみよう~^^
で、まず取り掛かるのは、短歌入口の人からですね。→小川真理子さんです。
こちらの方は、フランス語非常勤講師を仕事にしておられます。
言語の世界に深く根づいた短歌をお詠みです。
また、外国に留学されている時に、軽いカルチャーショックを受けておられる模様を短歌で表現しておられます。
この方、実はジャパニーズにしてはドライな感じの人なのかな?と思ったりします。
自分が共感した短歌を一つ。
ランボーに逢いにゆきたし贋札の両替のやうな会話を抜けて
ランボーはご存知ですか?ティーンエイジャーの時代にドカーンと謎の詩や散文を残し、20歳になったら、アフリカに消えた謎の怪人です^^
言葉に寄り添う仕事をする人たちは、その言語のバックトーンである文化や、またその文化を発祥せしめたその土地の気候や地形に敏感です。
そのことが読み取れる短歌を2つ
雨の名の乏しきフランスの雨よ、降るならばわが巡りに降れよ
甘辛き味を知らざる口をもてouiかnonかと問ひ詰めてくる
言語に寄り添う歌二つ
「真理」といふ意味消えてゆく、横文字で指名登録欄を埋むれば
真理といふ名前の理由問ふたびに丸顔ゆゑとはぐらかさるる
どうやら、名前で哲学なさったようですね。
この方、どうやら自分を達観しておられるようです。
日本にいるときにはフランスの目線が背後に、フランスにいるときには日本の視線が背後に潜んでいる感じでしょうか。
あほらしき渾名つけられはしやぎをりあつけらかんと好きと言ふため
すごいなー戦略を練っておられましたか~という感じですね^^;
この歌、ドライ⇔ウエット ドライ⇔ウエット という構造になっている気がします。
あほらしき→ドライ はしゃぐ→ウエット あっけらかん→ドライ 好き→ウエット
湿度の違いだけで考えれば、フランスと日本を2周巡った感じでしょうか。
後、言語というものは、古来から代々受け継いできたものなので、歴史を感じさせられる表現が多々あります。
たとえば、祭り事という言葉は政治のことですが、平安時代位までは本当に、祭りを執り行うことが政治だったりしたのです。神様の機嫌を取る→豊作とか。
こんな歌があります。
共にゐる時間は眠りに充てられて土のなかなるわれらならむか
この歌が詠まれた時は、すでに結婚されておられるようですが、夫君がジャーナリストの方らしく、特に中東に赴かれることが多いようで、なかなか夫婦の時間が取れない感じです。
この、土のなかなるわれらならむか が好きです。なんかすごく太古な雰囲気をたたえておいでです。土の中というのは、ママンのおなかの中です。土は女神として祭られていることが多いと思います。
ユングはグレートマザーと表現しています。
言語と密接な関係にある人は、その言語の文化背景などにも興味をもたれるのだと思います。
文語体が多いのが好きです^^
次はフランス語教師の発音に対する敏感さが見えてくる歌を一つ。
舌の上で紙風船が弾むんだ「ぽるとがる」つて行つてごらん
騙し絵の窓辺より風 洋古書の蝋紙(パピエ パラフィネ)はつかに震ふ
火をくぐりぬけたる者の寂かさよ磁気人形(プぺ・ドゥ・ポルスレンヌ)は瞬きもせず
この歌集の題名が母音梯形なだけに、ここら辺の歌は、重要と思われます。母音梯形いというのは、発音するときに口の中がどんな感じになればいいのかを図に示したものだそうです。
むむ、何だか、未知の発音に触れてみたくなってまいりました。
ではではこの辺で今日は終いにしとうございます^^
(小川さん、勝手な理解でごめんなさい~^^)