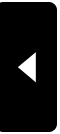白川静氏の著作を読んでいます。
といっても、氏の文章はむずかしく、私のような読書力の少ない者には荷が重い感じですw
でも、あつかっている事柄にはとても興味があり、ゆえに頑張って読んでいる次第です。
最近、平凡社の「漢字の世界」という本をかじりましたw(読みましたとは到底言えないのでw)
1と2に分かれているのですが、二冊目の最初の、「言霊の信仰」の最初を頑張って読みました。
言葉は、他人との意思の疎通に関してよりも、神との意思の疎通の必要に至った時にばりばりっと発達したという事です。
(本文は難解な用語で記されているため、わたくしの言葉で表現しました)
神との意思の疎通としての言葉は、それ以前のような気楽なものではなくなって、言霊というものを孕むようになります。
言葉は人の内部に潜む内容を外側に表す、すなわち「はなす」(離す)つまり当人の意思を離れます。
そして、それを形象化して、「かたる」(形(ちづく)る)。
こんな風に日本語の中に言葉の仕組みを物語る言葉があったとは驚きでした。
話す(離す)ことは自分の中にある思いを、野に放つことを言うという事でしょうか。それ故に言葉は自立した存在とも言うべきものになって、言霊として作用するということだろうと思います。
万葉集からの引用がありました。
言に出でていわばゆゆしみ朝貌(あさがお)の穂には咲き出ぬ恋もするかも
(ことばに出して言ったら恐ろしいので朝顔の花のように人目を引くことのない恋もすることだ)(万葉集二 講談社文庫)
ひそかな恋愛においても、それを口に出すのがはばかられるのは、言霊を意識しているからだそうです。
よく、「縁起でもないことを言わないでよ」という人がいますけれども、これは無意識のうちに言霊を信仰しているという事と言えましょう。
そして、一つの漢字をこれらのことに関して解説することができます。
「言」という漢字です。
この語の下の口は口のことではなく、古代の祭事に使われた道具で、祝告や誓いの文書を収める器であるそうです。
そして、上部の横線四本は、「辛」のことであるとのことですが、この漢字は、入れ墨をするための針の形であるとのことです。
つまり、言という漢字は、何かの誓いをする時に、それをたがえた時には入れ墨による刑罰をも辞さないという厳しい意味があるのでした。
古代社会は、言葉一つ話すのも細心の注意が必要だったんですね~おお怖い。。。
といっても、氏の文章はむずかしく、私のような読書力の少ない者には荷が重い感じですw
でも、あつかっている事柄にはとても興味があり、ゆえに頑張って読んでいる次第です。
最近、平凡社の「漢字の世界」という本をかじりましたw(読みましたとは到底言えないのでw)
1と2に分かれているのですが、二冊目の最初の、「言霊の信仰」の最初を頑張って読みました。
言葉は、他人との意思の疎通に関してよりも、神との意思の疎通の必要に至った時にばりばりっと発達したという事です。
(本文は難解な用語で記されているため、わたくしの言葉で表現しました)
神との意思の疎通としての言葉は、それ以前のような気楽なものではなくなって、言霊というものを孕むようになります。
言葉は人の内部に潜む内容を外側に表す、すなわち「はなす」(離す)つまり当人の意思を離れます。
そして、それを形象化して、「かたる」(形(ちづく)る)。
こんな風に日本語の中に言葉の仕組みを物語る言葉があったとは驚きでした。
話す(離す)ことは自分の中にある思いを、野に放つことを言うという事でしょうか。それ故に言葉は自立した存在とも言うべきものになって、言霊として作用するということだろうと思います。
万葉集からの引用がありました。
言に出でていわばゆゆしみ朝貌(あさがお)の穂には咲き出ぬ恋もするかも
(ことばに出して言ったら恐ろしいので朝顔の花のように人目を引くことのない恋もすることだ)(万葉集二 講談社文庫)
ひそかな恋愛においても、それを口に出すのがはばかられるのは、言霊を意識しているからだそうです。
よく、「縁起でもないことを言わないでよ」という人がいますけれども、これは無意識のうちに言霊を信仰しているという事と言えましょう。
そして、一つの漢字をこれらのことに関して解説することができます。
「言」という漢字です。
この語の下の口は口のことではなく、古代の祭事に使われた道具で、祝告や誓いの文書を収める器であるそうです。
そして、上部の横線四本は、「辛」のことであるとのことですが、この漢字は、入れ墨をするための針の形であるとのことです。
つまり、言という漢字は、何かの誓いをする時に、それをたがえた時には入れ墨による刑罰をも辞さないという厳しい意味があるのでした。
古代社会は、言葉一つ話すのも細心の注意が必要だったんですね~おお怖い。。。