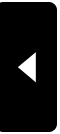こんにちわ~とぅらんく芸術鑑賞部部長です~^^
本日、我が部活内で新しく活動し始めた、文学友の会の人を紹介します^^
こんにちわ~文学友の会です~^^
私の活動範囲は、小説やエッセイを読んで、感想を述べたり、皆さんにご紹介することです^^
さっそくですが、タイトルの題名にしていただいた小説についてお話したいと思います。
この本です。

この本を見つけたのは2002年でした。偶然図書館で見つけました。
この時期、映画で「戦場のピアニスト」が公開されておりました。
友人と見に行く予定にしておりましたが、先にこの本を読みました。
いずれも、不幸なピアニストのお話です。
戦場の…の方はユダヤ人ピアニストでしたね。ショパンのノクターン第20番を弾いておられました。
そして、こちらのピアニストさんは、旧ソ連の人です。
リサイタルを目前に控えておられましたが、場所は共産圏。え、そんなことで追われる身になってしまうなんて!という事態発生で、身を隠す日々がやってまいります。
戦場の…のピアニスト殿は、ゲットーから強制収容所に連れて行かれそうになった時に、有名なピアニストだからという理由で助けられてしまい、家族と生き別れになります。
どちらのかたも、ピアノを目前にして、身を隠す身なので、音を立てられず、エアピアノのシーンがあり、切ないです。
戦場の…の人はとあるドイツ軍将校の前で、ためらいながらも、今までの気持ちをぐあっとピアノにぶつけるシーンがありました。見どころだと思います。
この親切な将校、後に戦犯で殺されてしまいますが……
で、ソビエトのピアニスト殿は名前を隠して軍人生活を送りますが、最後の方で、上司の娘さんのピアノのお相手をさせられます。
なんと娘さんからピアノを習わなくてはならないという試練です。
当然、へったくそを装わなければならないのですが、所々で、ちょっとしたミスが出ます。
「ここはシャープが一つついてる」
と、ぼそっと言ってしまったりします。
最後にその家でパーティーが催され、その時に、将校の娘の育てたピアノの生徒として、ピアノを弾かされます。観衆の御望み通り、また、娘の思う通りに弾かなければならない。
そして、お望みの通り一曲をへたくそ演奏しますが、
「さあ、今度はプログラムのハイライト、「鳩のワルツ」です!」。
と娘に紹介された時、彼は両手のヴェールをにはがして、ついにピアニスト登場!で、終わるんです。
このときの表現を少し引用。
彼が再び手を鍵盤に降ろしたときには、みんなはまだ、美しいハーモニーが彼とは関係なく偶然に出来上がったものだと信じることができた。けれど一秒後には音楽が波のように押し寄せ、疑いも話し声も物音もその力強さによって運び去られ、浮かれ顔も交わられていた視線も消し去られ、壁という壁は遠く押しのけられ、サロンの光は窓の向こうの広大な夜空に散っていった。
むろん、流刑ですね。シベリア抑留です。
戦場のピアニスト殿は、苦難に苦難を経て、再びピアノを弾くことが出来るようになったのですが、
ソビエトのピアニスト殿は、もう二度とピアノを弾くことが出来なくなりました。
でも、とあるパーティーにおける、ピアニスト突如現る事件は、とても素敵と思いました。
何もかもをかなぐり捨てて、その一瞬に、突如、へたなもの習いの軍人が、光り輝くピアニストとなる、この一瞬、ちょっと欲求不満になりそうですが……
この本、本としての形も好きです。表紙はたぶん鉛筆画ですかね、細密にソ連の兵士が描かれています。
目のあたりがうつろで、この本の内容をほうふつとさせます。
また、本文の厚さも暑すぎなく、薄すぎることもなく、ページを開きますとヘッダーよりもフッダーの方が
若干広めにとってあって、バランスが良いです。散文詩みたいに読めます。
上の引用を少し読んでいただいただけでも、これって、小説?詩なんじゃないの?って思われるのではないでしょうか。
作者は「アンドレイ・マキーヌ」と言う人です。ロシア産まれの人ですが、フランスで小説を書いてます。ほかの資料には、亡命した、って書かれていたような気がしますが、ソ連の暴挙をフランスで小説という形で暴露しています。
興味のある方はぜひぜひ読んでみてくださいませ。
本日、我が部活内で新しく活動し始めた、文学友の会の人を紹介します^^
こんにちわ~文学友の会です~^^
私の活動範囲は、小説やエッセイを読んで、感想を述べたり、皆さんにご紹介することです^^
さっそくですが、タイトルの題名にしていただいた小説についてお話したいと思います。
この本です。
この本を見つけたのは2002年でした。偶然図書館で見つけました。
この時期、映画で「戦場のピアニスト」が公開されておりました。
友人と見に行く予定にしておりましたが、先にこの本を読みました。
いずれも、不幸なピアニストのお話です。
戦場の…の方はユダヤ人ピアニストでしたね。ショパンのノクターン第20番を弾いておられました。
そして、こちらのピアニストさんは、旧ソ連の人です。
リサイタルを目前に控えておられましたが、場所は共産圏。え、そんなことで追われる身になってしまうなんて!という事態発生で、身を隠す日々がやってまいります。
戦場の…のピアニスト殿は、ゲットーから強制収容所に連れて行かれそうになった時に、有名なピアニストだからという理由で助けられてしまい、家族と生き別れになります。
どちらのかたも、ピアノを目前にして、身を隠す身なので、音を立てられず、エアピアノのシーンがあり、切ないです。
戦場の…の人はとあるドイツ軍将校の前で、ためらいながらも、今までの気持ちをぐあっとピアノにぶつけるシーンがありました。見どころだと思います。
この親切な将校、後に戦犯で殺されてしまいますが……
で、ソビエトのピアニスト殿は名前を隠して軍人生活を送りますが、最後の方で、上司の娘さんのピアノのお相手をさせられます。
なんと娘さんからピアノを習わなくてはならないという試練です。
当然、へったくそを装わなければならないのですが、所々で、ちょっとしたミスが出ます。
「ここはシャープが一つついてる」
と、ぼそっと言ってしまったりします。
最後にその家でパーティーが催され、その時に、将校の娘の育てたピアノの生徒として、ピアノを弾かされます。観衆の御望み通り、また、娘の思う通りに弾かなければならない。
そして、お望みの通り一曲をへたくそ演奏しますが、
「さあ、今度はプログラムのハイライト、「鳩のワルツ」です!」。
と娘に紹介された時、彼は両手のヴェールをにはがして、ついにピアニスト登場!で、終わるんです。
このときの表現を少し引用。
彼が再び手を鍵盤に降ろしたときには、みんなはまだ、美しいハーモニーが彼とは関係なく偶然に出来上がったものだと信じることができた。けれど一秒後には音楽が波のように押し寄せ、疑いも話し声も物音もその力強さによって運び去られ、浮かれ顔も交わられていた視線も消し去られ、壁という壁は遠く押しのけられ、サロンの光は窓の向こうの広大な夜空に散っていった。
むろん、流刑ですね。シベリア抑留です。
戦場のピアニスト殿は、苦難に苦難を経て、再びピアノを弾くことが出来るようになったのですが、
ソビエトのピアニスト殿は、もう二度とピアノを弾くことが出来なくなりました。
でも、とあるパーティーにおける、ピアニスト突如現る事件は、とても素敵と思いました。
何もかもをかなぐり捨てて、その一瞬に、突如、へたなもの習いの軍人が、光り輝くピアニストとなる、この一瞬、ちょっと欲求不満になりそうですが……
この本、本としての形も好きです。表紙はたぶん鉛筆画ですかね、細密にソ連の兵士が描かれています。
目のあたりがうつろで、この本の内容をほうふつとさせます。
また、本文の厚さも暑すぎなく、薄すぎることもなく、ページを開きますとヘッダーよりもフッダーの方が
若干広めにとってあって、バランスが良いです。散文詩みたいに読めます。
上の引用を少し読んでいただいただけでも、これって、小説?詩なんじゃないの?って思われるのではないでしょうか。
作者は「アンドレイ・マキーヌ」と言う人です。ロシア産まれの人ですが、フランスで小説を書いてます。ほかの資料には、亡命した、って書かれていたような気がしますが、ソ連の暴挙をフランスで小説という形で暴露しています。
興味のある方はぜひぜひ読んでみてくださいませ。