こんばんわ~とぅらんく芸術鑑賞部です~^^
ずいぶん長いこと眠ったままで、エコノミー症候群になっちゃいそうな今日この頃orz
血液がドロドロになってしまわないように音楽を聴くことにしたよ~w
今日は、ふっ、とショパンのノクターン第八番を聴きたくなりました。
ショパンのピアノはいろんな感情が入り込んでいて、うわ~湿度高!という感じですね~
その極みの一つですね、この曲。
出だしが長調なんですけど、すぐに鬱積するあたり、そのあたりのところが好きです。
初めに聞いたのは、ホルヘ・ボレットというピアニストさんによる演奏でした。
老境の極みという感じです。
もう一つ、ダニエル・バレンボイム氏の演奏ですが、先にホルヘ・ボレット氏による演奏を聴いた後に聴きましたところ、
(ややこしい言い回しだなw)
バレンボイム氏の演奏は標準な感じがしてしまいました。
そのように思ったのは、今から5年前くらいなので、改めて聴きなおしてみました。
まず先に、ダニエル・バレンボイム氏の演奏を聴きました。
聴いてみて、あれ、良いじゃん、繊細なタッチで表現されているなと思いました。
デリケートなところを大切にしているのが伝わってきましたですよ。
その後に、ホルヘ・ボレット氏の演奏を聴きました。
5年前、この人の繊細なタッチに惹かれていたのですが、なぜ、そこのところに惹かれたのかが解りました。
この人の演奏は全体的にダイナミックだということです。
中ほどの繊細なあたりにたどり着く前のあたりで、ぐわっとテンションを上げているので、その次に気分が変わるとき、そのあたりが存分に引き出されてより一層繊細に聞こえました。
ということで、またもやホルヘ・ボレット氏に軍配が上がりました。
この度聞いたのは、1987年6月のロンドンで録音されたホルヘ・ボレット氏のピアノと、
1981年1月にベルリンで録音されたダニエル・バレンボイム氏のピアノです。
クラシックの聴き比べって、最近全然してなかったから、たまにはやってみるのもいいなあ~
そして、表題の件ですが、メンデルスゾーンでなくてごめんなさいw
ずいぶん長いこと眠ったままで、エコノミー症候群になっちゃいそうな今日この頃orz
血液がドロドロになってしまわないように音楽を聴くことにしたよ~w
今日は、ふっ、とショパンのノクターン第八番を聴きたくなりました。
ショパンのピアノはいろんな感情が入り込んでいて、うわ~湿度高!という感じですね~
その極みの一つですね、この曲。
出だしが長調なんですけど、すぐに鬱積するあたり、そのあたりのところが好きです。
初めに聞いたのは、ホルヘ・ボレットというピアニストさんによる演奏でした。
老境の極みという感じです。
もう一つ、ダニエル・バレンボイム氏の演奏ですが、先にホルヘ・ボレット氏による演奏を聴いた後に聴きましたところ、
(ややこしい言い回しだなw)
バレンボイム氏の演奏は標準な感じがしてしまいました。
そのように思ったのは、今から5年前くらいなので、改めて聴きなおしてみました。
まず先に、ダニエル・バレンボイム氏の演奏を聴きました。
聴いてみて、あれ、良いじゃん、繊細なタッチで表現されているなと思いました。
デリケートなところを大切にしているのが伝わってきましたですよ。
その後に、ホルヘ・ボレット氏の演奏を聴きました。
5年前、この人の繊細なタッチに惹かれていたのですが、なぜ、そこのところに惹かれたのかが解りました。
この人の演奏は全体的にダイナミックだということです。
中ほどの繊細なあたりにたどり着く前のあたりで、ぐわっとテンションを上げているので、その次に気分が変わるとき、そのあたりが存分に引き出されてより一層繊細に聞こえました。
ということで、またもやホルヘ・ボレット氏に軍配が上がりました。
この度聞いたのは、1987年6月のロンドンで録音されたホルヘ・ボレット氏のピアノと、
1981年1月にベルリンで録音されたダニエル・バレンボイム氏のピアノです。
クラシックの聴き比べって、最近全然してなかったから、たまにはやってみるのもいいなあ~
そして、表題の件ですが、メンデルスゾーンでなくてごめんなさいw


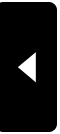

僕はクラシック聴いていたのは子供の頃だなあ。中学生の時に、かわいい女性の若い音楽教師になついていたよ。wwそれが目的かっ(笑)
僕、ちょっとまえに、その子どものころに聞いていたCDを、Amazonの中古で買い直しました。
エリック・サティのCDで、フィリップ・アントルモンの演奏の。
サティを演奏する人って鬱屈する表現がおおいけれど、アンモルトンの演奏表現は、「サティはこういうのを表現したくて書いたんだろうな」っていうくらい正統派で、素直な演奏でした。
でも十数年ぶりに聞き直したら、素直すぎてそっけなかったかも。
僕はモーツアルトが好きで、「バイオリン パルティータとソナタ」が好きだった。かわいい女性の若い音楽教師に(大切なことは二度言うw)、教えてもらった曲だから。
いや~いろいろ教えてくださってありがとうございますw
「かわいい女性の若い音楽教師」さんになついておられたのですねww
魅力的な教師に教えてもらうと入りやすい、というのもあるんだと思いますw
サティですか、きちんと聞いたことがまだないです。
また探してみますね。
モーツアルトが好きというのは正統派な感じですね。
私はクラシック、モーツアルトからは入れなかったです。
でも、「クラリネット五重奏曲」なら入っていけます。
「バイオリン パルティータとソナタ」ですか~
モーツアルトはまだ未開拓なところがあるので、もう少し幅を広げてみようかな。
で、ショパンですがw
ピアノ曲の入門版があるとおもいますので、それから入ると入りやすいですよ。
エヴァンスでも、キース・ジャレットでも、ピアノソロって
どこか聴いていて不安な気持ちになるのかも。
きっと、ベースとドラムのサポートがないと、なんだか不安で落ち着いて聴いていられないみたい。
あとウチのオーディオが、ピアノソロとかクラシックの音楽には相性が悪いの・・・。
低音部と、管楽器を強く出そうとするから。(だからジャズ向きではあるんだけれど)
パルティータとソナタはバイオリンのソロ演奏なんだけれど、ちょっと(ていうかかなり)クセがあるよ。
僕自信も、記憶にはあるけれど、いま聴けるかっていったら、クセの強さについていけないかも。
エバンスは耽美派で、内面的だし、キースもまた、ECMというレーベルの代表格の一人だから、内面的な表現になりやすいですね。
私はそこが好きなんですけど、なみきさんは感受性が鋭い感じがするから、敏感に響いてしまうんでしょうね。
でも、それって短歌を詠む時にはすごくプラスになりそうですね。
アララギのモットーを体現しているみたいな感じがします。